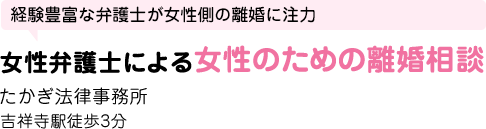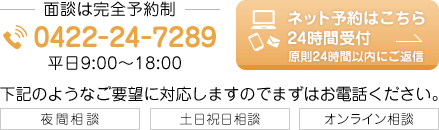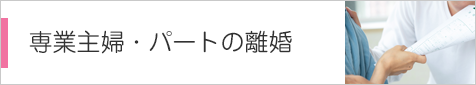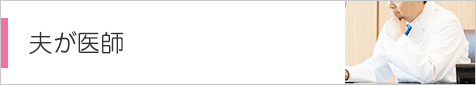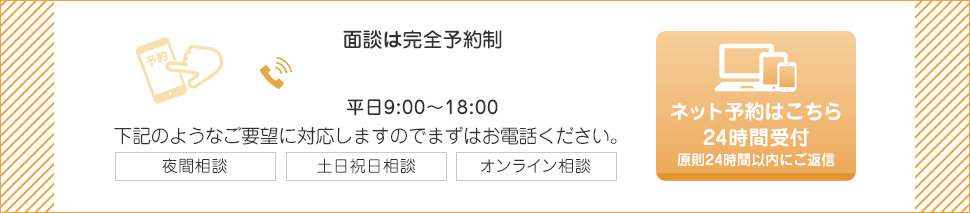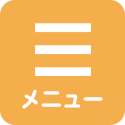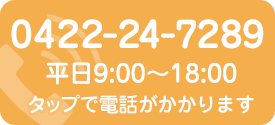夫が医師
夫が医者で高収入の場合、収入や資産が多いだけでなく、特有の問題もあることも念頭に準備を進める必要があります。よくある問題点についてまとめました。
目次
1 婚姻費用・養育費関連
別居中の婚姻費用(生活費)や離婚後の養育費は、双方の収入を基に算定表に基づいて計算されます。
(1)収入資料(勤務医の場合)
医師の収入を示す資料としては、勤務する病院からの給与を示す源泉徴収票があります。しかし、勤務医の場合、複数の病院で勤務している場合があるので、収入の全てが反映されている確定申告書の控えか課税証明書で収入の合計を確認しましょう。
住民登録上、同じ世帯にある妻は、夫の課税証明書を市区役所で取得することが出来ることが多いので、夫の課税証明書を取得して確認しましょう。
医師は、社会保険から診療報酬を受けていることが多いので、診療報酬の支払い元である、国民健康保険団体連合会や社会保険診療報酬支払基金事務所に診療報酬の支払明細の開示を弁護士会や裁判所を通じて求めて収入が判明することもあります。
(2)収入資料(開業医の場合)
開業医の場合、自営業であるので、収入資料として確定申告の控えや課税証明書が出されることが多いです。
しかし、確定申告に記載されている数字は、その数字を反映した課税証明書は、夫が自ら申告したものですので、操作され低く抑えられていることが多いです。
そのため、確定申告の数字を基に婚姻費用や養育費を決めようとすると、その額が非常に低い額になってしまうことがあります。
もし、確定申告上の数字が、同居中や別居後の夫の生活実態とかけ離れて少額な場合で、同居中の家計など証明できる場合は、実態に即した年収を前提に婚姻費用や養育費を算定してもらえる可能性があります。
例えば、同居中、月50万円程度は生活費として使っていたにも関わらず、確定申告の年間所得が300万円程度しかない場合、確定申告の数字ではなく、実際の支出に即した年収と想定して判断される可能性があります。
(3)算定方法
家庭裁判所のホームページに掲載されている婚姻費用・養育費算定表(「算定表」)を使用して金額を出すのが通常です。
しかし、夫が医師の場合、その収入が算定表に記載されている最高額(給与所得者は2000万円、自営業者は1567万円)より高額であることも少なくありません。その場合、婚姻費用分担額や養育費については、どのように算出するのでしょうか。
➀ 婚姻費用
義務者の収入が算定表の最高額を500万円超える程度の場合、算定表の最高額を上限とする方法が取れられることが多いです。
義務者の収入が算定表の最高額から500万円以上多く、1億円未満程度の場合は、基礎収入の割合を修正する方法を用いられることが多いです。
基礎収入の割合というのは、公祖公課、職業日、特別経費を除く割合ですが、収入に応じて数値が変わってきます。その上限の数値(給与所得者は34%、自営業者は47%)を少し低くするというのが、基礎収入割合を修正する方法です。
義務者の収入が1億円を超えるような場合は、同居中の生活レベルや生活費の支出状況、現在の生活費支出状況を検討して、必要分を加えて判断します。
このように出された婚姻費用分担額に特別にかかる教育費等があれば、それも加算して決めることになります。
② 養育費
養育費については、婚姻費用の考え方とは違い、算定表の最高額を上限をする例が多いです。もっとも、算定表の金額に教育費用など加算することはあります。
➂ 教育費
親が医者の場合、その子も医学部に進学することは普通の流れです。そのため、私立の医学部進学であっても、私立医学部進学に明示又は黙示の同意があり、親の収入から学費負担が問題ない状況であれば、私立医学部学費についても養育費に加算して認められる可能性が高いです。
【大阪高等裁判所平成29年12月15日決定(判例タイムズNo1451-109)】
父が医師、母が薬剤師。父母の離婚後に子が二浪後、私立医学部に進学し、子が父親に私立医学部の学費を扶養料として支払うことを求めたケース。大阪高裁は、父が離婚時、子が私立医学部へ進学することも想定していたとし、標準的算定方式で算定される額で賄えない部分の扶養料を父母の収入などの状況に応じて分担すべきとしました。
2 妻が従業員として働いている場合
夫が医院を経営していて、妻を従業員として雇用している場合があります。
この場合、夫婦間で別居や離婚の問題が発生したからといってそれを理由に夫が妻を解雇することは出来ません。解雇するためには労働契約法上の客観的合理的な解雇理由が必要です。そのような解雇事由がないもかかわらず、解雇した場合、妻は、夫か夫の法人に対し、解雇無効の裁判を起こすことが出来ます。
ですので、離婚の話し合いの中で、妻が従業員として勤務していた点も含めて話し合いをする必要があります。
3 医師の財産分与
(1)法人ではない個人医院経営の場合
個人経営の場合は、事業財産の場合でも婚姻中に取得したものであれば、財産分与の対象になるのが原則です。
この場合、事業用のプラスの財産だけでなく、マイナスの財産(借入)も計上することになります。
医院の開業には、多額の資金が必要で、多額の婚姻財産をつぎ込み、さらに、多額の融資を受けて開業した場合、離婚時の財産は、借金の方が多いという場合もあり得ます。医院の経営が順調で収益も安定しており、借金も減っている場合、婚姻財産としてマイナスだから財産分与は無しとするのは、公平を欠きます。この場合は、数年分の収益や、どのくらい借金が減ったかなどを考慮して、財産分与額を決めることも考えられます。
(2)医療法人経営の場合
原則として、医療法人は、財産分与の対象になりません。
婚姻前に設立した医療法人は、出資持分がある場合(平成18年医療法改正前)でも、それはその医療法人を設立した配偶者の特有財産になるので、財産分与の対象にはなりません。
婚姻後に設立した医療法人は、出資持分がある場合(平成18年医療法改正前)は、その出資持分は、財産分与の対象になります。
出資持分が財産分与の対象になる場合、出資持分をいくらと評価するかの問題があります。裁判所は、純資産方式(直近事業年度の決算書の純資産額を総出資額で除して持分1口当たりの金額を算定する方式)をとることが多いようです。もっとも、純資産額に比べて、安定した高い収益を得ている場合は、純資産方式だけでなく、収益還元方式(収益性に着目して将来得られるであろう価値を算出する方式)も併用されることもあります。もっとも、医療法人は会社とは異なり、すぐに持分を払い戻しすることが想定されていないこともあるため、純資産額から一定の減額をした額を分与財産とされることもあります。
【大阪高等裁判所平成26年3月13日決定(判例タイムズNo.1411-177)】
夫が医療法人経営(出資持分あり)しているケースで、出資持分の評価につき、純資産方式を採用し、出資払い戻しも制限されていて、医師である夫が出資の払い戻しをするときまでの医療法人の運営状況について予想しがたいことから、出資持分評価額の7割を婚姻財産としました。
婚姻後に設立した医療法人でも、出資持分がない場合(平成18年医療法改正後)は、原則として財産分与の対象になりません。もっとも、医療法人の設立に際し、多額の婚姻財産を投入し、医療法人が安定した収益を出している場合、医療法人に関して、何の財産分与しないのは、不公平な結果になります。その場合は、医療法人の収益などから分与すべき金額を決めることも考えられます。
(3)退職金
夫がクリニックの理事等をしている場合、勤務医ではないから退職金はないのではないかと思いがちです。しかし、多くの病院は、理事の退職金のための保険(長期平準定期保険、逓増定期保険など)に加入しています。ですので、退職金についても忘れずに主張しましょう。
(4)小規模共済、個人年金
夫がクリニック経営の場合、小規模共済や確定型拠出年金(例えば、iDeco, 積み立てNISA)など、資産形成をしている可能性もあります。これらも財産分与に対象になりますので、忘れないように確認しましょう。
(5)財産分与の割合
財産分与の割合は、平等が原則で、平等ではないケースは非常に稀です。
ただ、平等ではないケースも、ゼロではありません。
その典型例が、開業医の場合です。
例えば、婚姻前に医師の資格を取り、しばらく勤務医をしていたが、婚姻中に開業し、高額な収入を得て、何億もの資産を形成するに至った場合、分与割合が平等でない可能性があります。
【大阪高等裁判所平成26年3月13日判決(判例タイムズNo.1411-177)】
夫が医療法人を経営する医師で、婚姻財産3億円あまりのケースで、裁判所は、高額な収入の基礎となる特殊な技能が、婚姻前の本人の個人的な努力によって形成され、婚姻後もその才能や労力によって多額の財産が形成されたとして、夫6妻4の割合で財産分与を認めました。
4 強制執行
婚姻費用や養育費を調停などで取り決めしたのに、医師である夫が払ってくれない場合、強制執行して回収する必要があります。
勤務医の場合は、給与の差し押さえを勤務先の病院や医療法人に行うことになります。開業医の場合は、診療報酬請求権を差し押さえます。